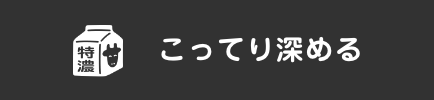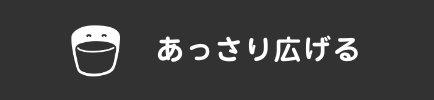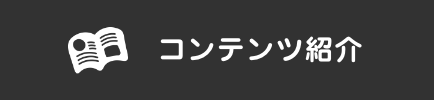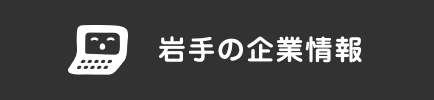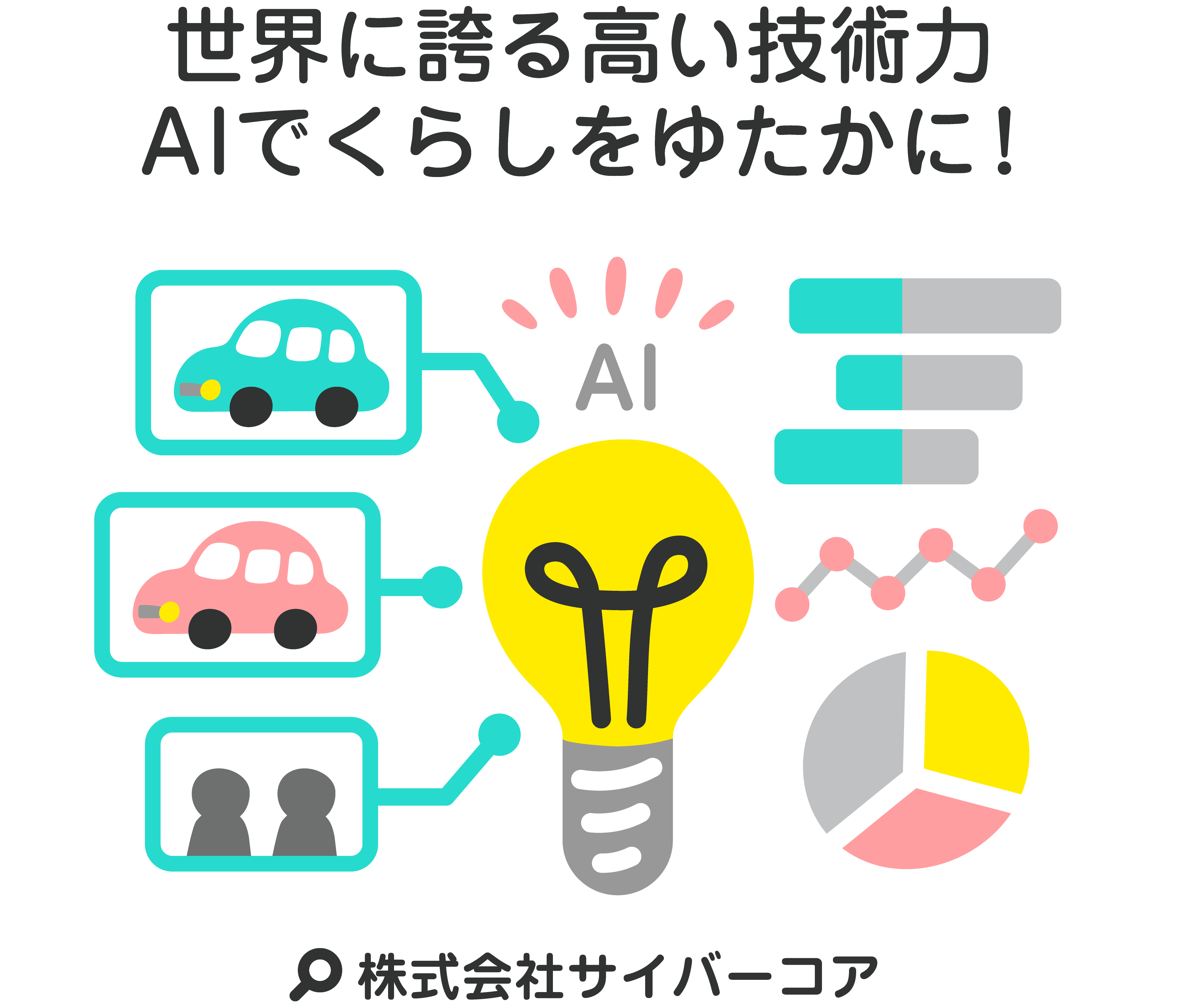interview
2025/10/28 掲載
あつまれ!熱血技術者/13
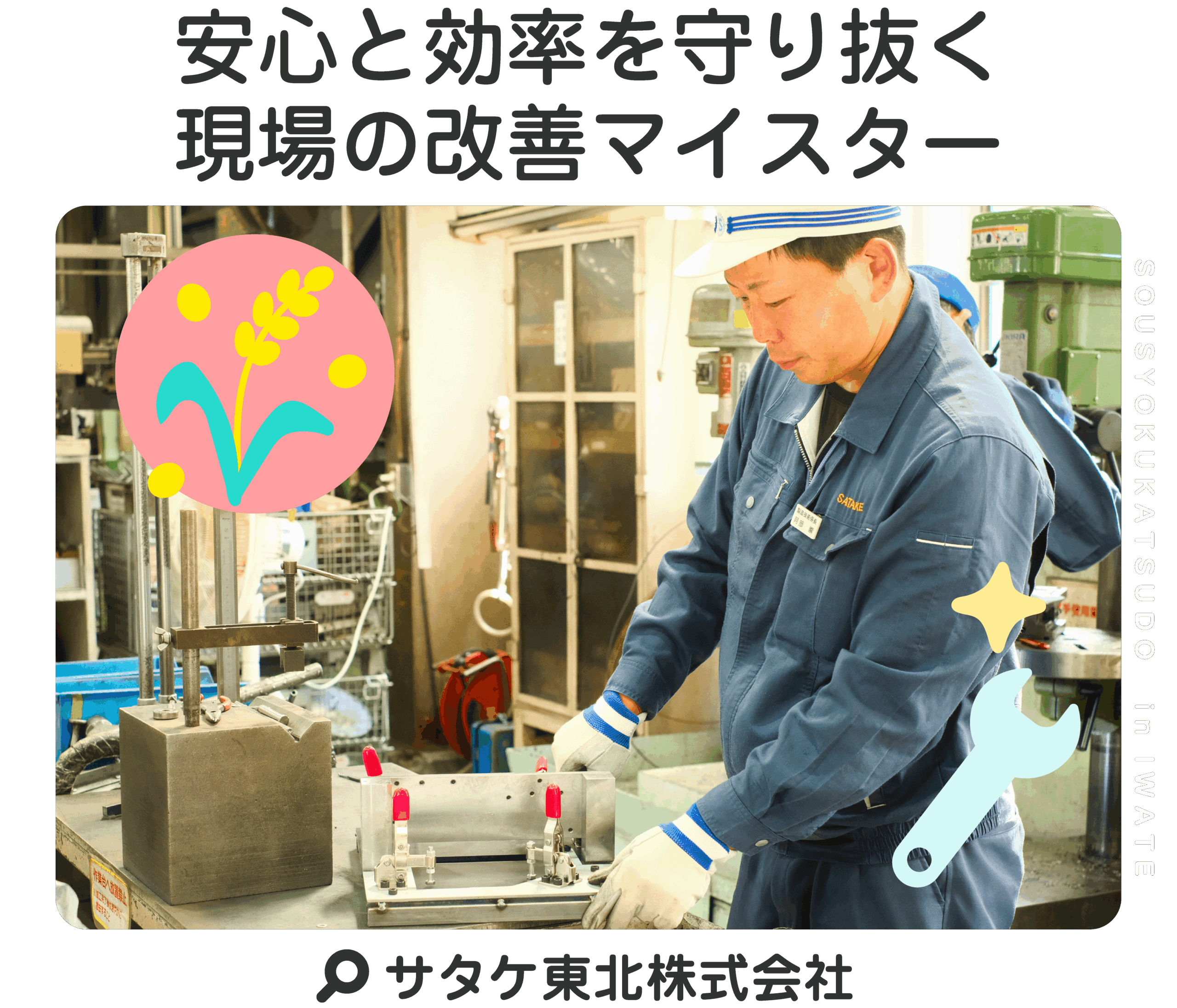
ものづくりに魅せられ、製品開発に心血を注ぐ技術者たち。彼らは、どんなことにこだわり、どうやって驚くようなアイデアを生み出すのか?日進月歩の世界で凌ぎを削る、熱き技術者たちに迫るこのコーナー。今回は北上市のサタケ東北株式会社の阿部瞬さんにインタビュー!
私たちが毎日食べているお米は、田んぼで収穫された後、いくつかの工程を経て出荷されています。稲刈り後の殻がついたお米は「籾(もみ)」と呼ばれますが、このままではまだ食べることはできません。刈り取った籾は乾燥させたのち、その外皮を取り除く「籾摺り(もみすり)」を行うことで玄米になります。さらに、玄米の表面についている茶色い層「ぬか」を削ることで、私たちが普段食べている白米になるのです。
サタケ東北株式会社は、こうした作業を行う穀類調整加工機械を製造しており、農家のパートナーとしても、私たちの食生活にも欠かせない存在です。


機械製造に必要な材料の調達から細かな部品づくりまで手がけ、穀類加工機械を完成させるまで一貫生産できるのがサタケ東北の強み。社内には、工場の製造ラインの安心と効率を守る専任の部署があります。
万一、トラブルが発生した時には、再発を防ぐために知恵を絞り、治具(じぐ)と呼ばれる作業を助ける特別な補助器具や自動ロボットを設計・導入したり、故障を修理したりしながら、スタッフが安心して働ける環境を整えていく———。いわば“改善マイスター”ともいえる「製造技術係」で係長を務める阿部瞬(あべ・しゅん)さんは、仕事の難しさをこう語ります。

「製造ラインの不具合や作業に支障が出ているときに、結論だけを急いで『こういうことでしょ』と改善策を現場に提案しても、現状をよく把握できていなければ、的外れで実効性のないものになりかねません。大切なのは、どの過程で、なぜ不具合が生じているのかを見極めること。それが人為的な要因なのか、システムの問題なのかを丁寧に探っていきます。
作業員のみなさんは、その都度環境に順応しながら作業を続けているので、多少のやりにくさも受け入れながら、仕事をすることが当たり前になっています。慣れている状態から原因を探り出すのが難しいところなんですが……。例えば、 本来5人で回す作業に10人がかりになっていたり、5時間で終わるはずが10時間かかっていたりと、そういった数値にも目を配りながら、現場で何度もヒアリングを重ねます。よりスムーズに生産できるように、作業員の負荷を少しでも減らすにはどうすればよいかを考えていくんです」

「実際に治具を使うのは現場の人たち。だからこそ、その声をよく聞くことが私たちの仕事の大事な部分です。最初から満点のものは作り出せない。それが難しさでもあるけれど、同時に楽しさでもありますね」
そんな風に話す阿部さんは、役職に関係なく作業員一人ひとりに話を聞くために、1日に少なくとも10回はデスクと現場を往復するのだとか。

「入社した頃は溶接をする部署にいたのですが、今ほど作業環境が充実していなかったので、体力的に大変でした。でも今は、ものづくりの現場を俯瞰して見つめながら、より良い環境を目指す製造技術係があります。直接売り上げを生む部署ではありませんが、動線を整えて作業時間を短くできれば、利益を生み出すことはできる。現場のみなさんの体力面にも気を配りながら、安心して働ける環境を守っていきたいと思っています」
現場の環境を整えることが、ものづくりの質につながっていく———。目に見えない工夫と配慮が、安心して働ける現場と高品質な製品を生み出していました。
(取材時期:2025年8月)
サタケ東北に興味を持った学生さんにメッセージ!
サタケグループの製品は世界各国の食文化向上に貢献しています。その中でサタケ東北では、主に日本国内で使用される農家・営農法人向けの穀類調製加工機械のほぼすべてを生産しています。北上から日本、そして世界へ。そんな大きな夢を持って働くことができる、それがサタケ東北です。

■サタケ東北株式会社
岩手県北上市に拠点を置き、お米の加工機械の設計・製造から部品加工まで一貫して行う、日本の農業を支えるメーカー。製造ラインの効率や安全性を高める装置も自社で開発し、高品質な製品と安心して働ける環境づくりを両立。地域の農業と食卓を支える頼れる存在です。
▶シゴトバクラシバいわて
https://www.shigotoba-iwate.com/kyujin/company/14000010061780