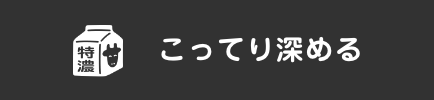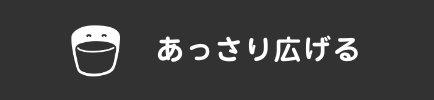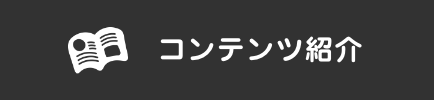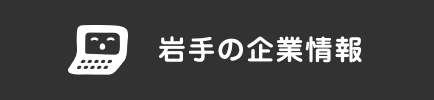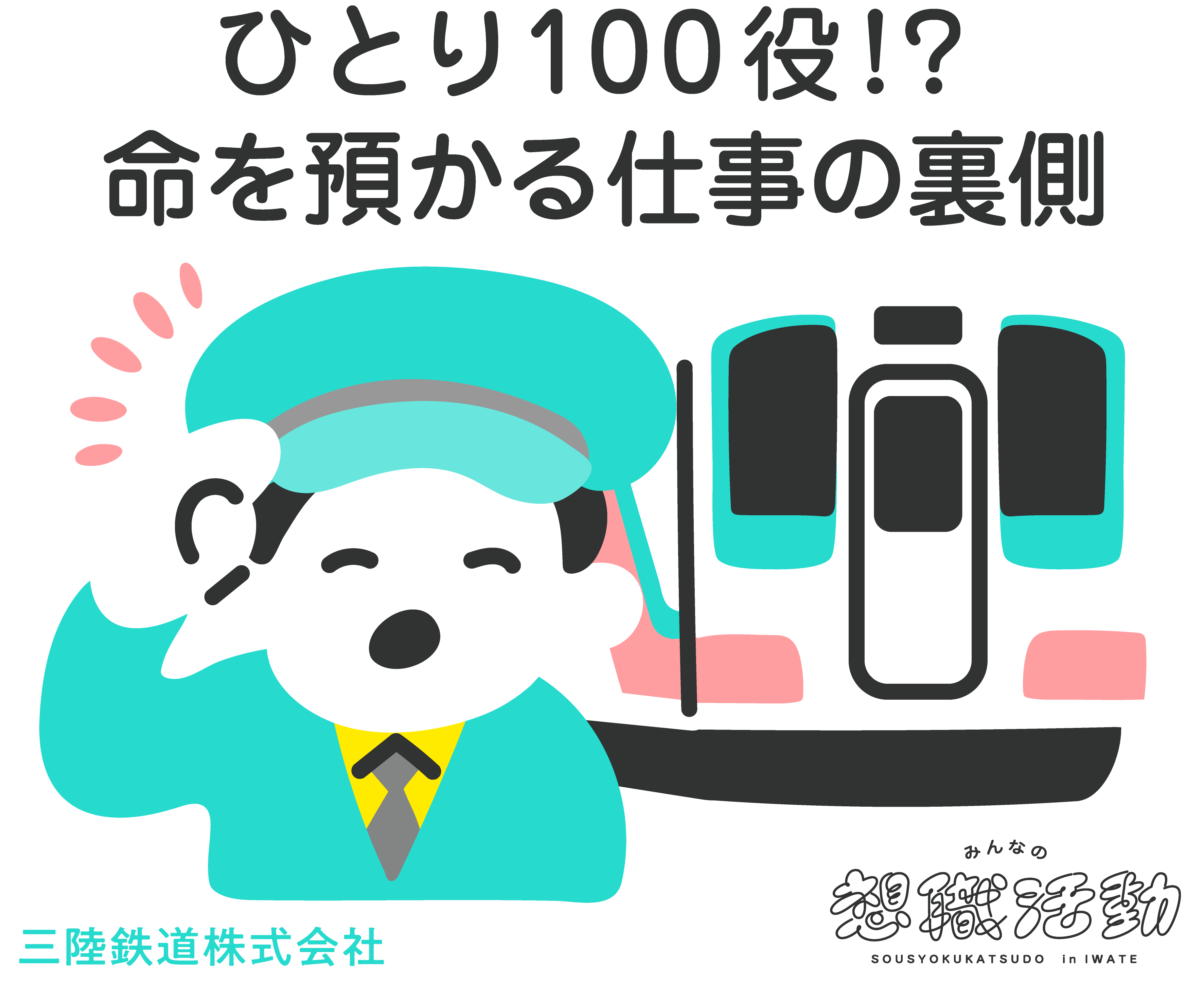interview
2025/9/10 掲載
こんな仕事があるのか岩手/16
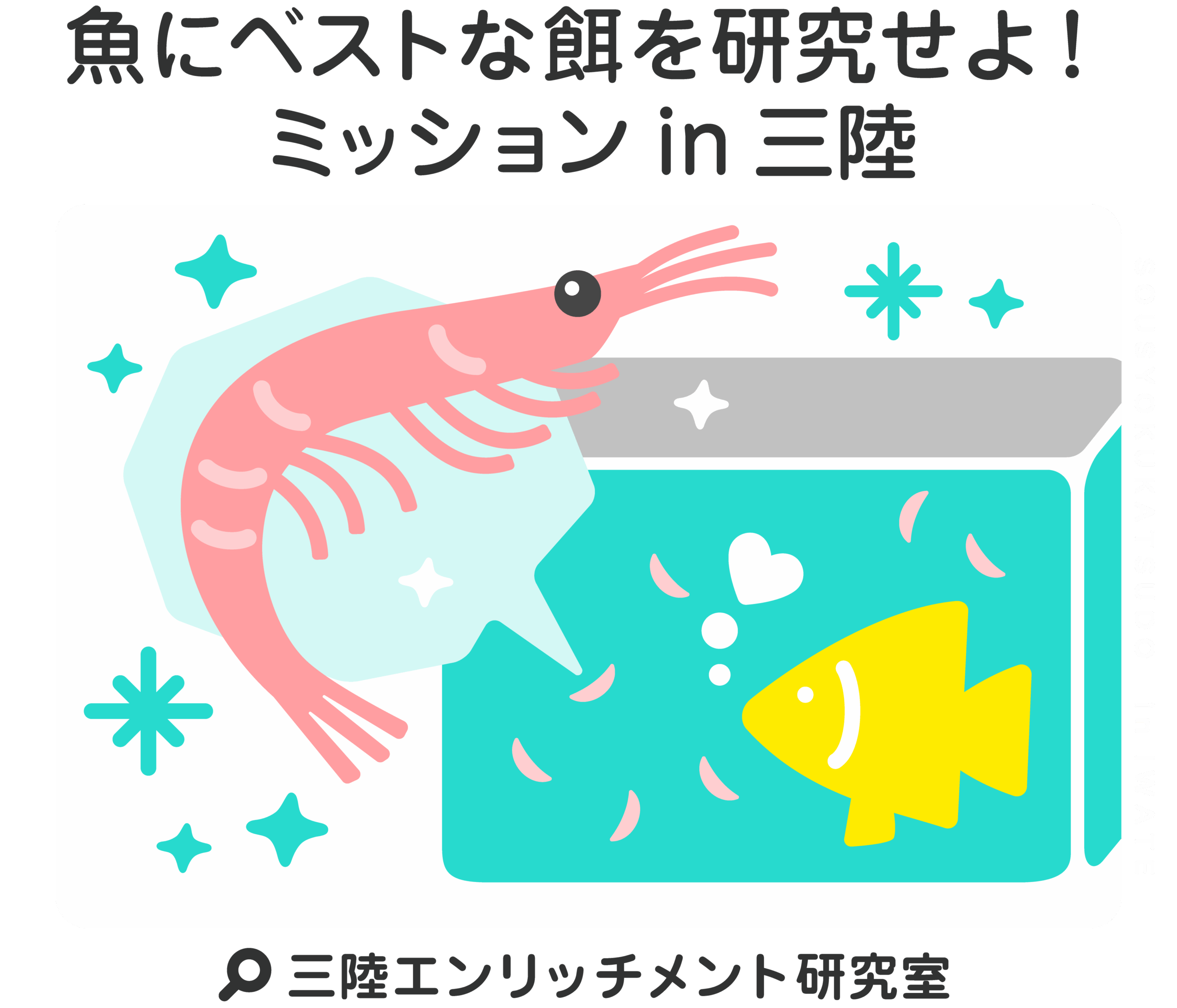
「地方は仕事が少ない…」と思っているとしたら、それ、誤解です。岩手には意外な職種や面白い仕事がいろいろあるんです。今回ご紹介するのは、岩手・三陸の海を舞台に観賞魚用の餌料を研究開発、販売する仕事。三陸エンリッチメント研究室の代表を務める土方剛史さんにお話をうかがいました。
みなさんは、金魚や熱帯魚など、家庭で魚を飼ったことがありますか? すいすい泳ぐ魚たちを見ていると、なんだか癒されますよね。これら観賞用魚には、取扱いやすさから「配合餌料」といって動物性たんぱく質やアミノ酸、ビタミンなどが人工的に配合された餌を与えるのが一般的です。
しかし本来、魚は生息環境に住む多様な生物の中から自ら餌を選んで食べています。魚は成長段階で体の大きさや消化システムが劇的に変わり、それに応じて栄養の必要性も変わります。人間に置きかえれば、肉や魚、野菜など多種多様な食材から様々な栄養を取っているのと同じです。一方、水槽にいる観賞魚には、餌を選ぶ自由はありません。
その成長段階に合わせた栄養をとるためには、より自然環境に近い餌の選択肢を増やすことが大切です。これ一つで良いといった万能な餌は存在しないからこそ、魚にとって最適な餌をどう与えるのかが課題となります。
それでは、本来の生息環境から切り離され水槽で生息する魚には、いったいどんな餌が適しているのでしょうか。「魚が自然の中で食べてきたものを、できるだけそのままの形で届ける」―その理念を掲げ、観賞魚用餌料の研究・製品開発を進めているのが、三陸エンリッチメント研究室。代表を務めるのは土方剛史(ひじかた・たけし)さんです。

三陸エンリッチメント研究室が研究開発し、販売している精密凍結・活餌料「Natural Ecosystem Module ®︎」は「プランクトンシリーズ」、「魚卵シリーズ」、「ベントスシリーズ」の3種類。さまざまな種類の観賞魚とのマッチングが調査されています。

東日本大震災による原発事故の風評被害で、当時イサダの魚価は暴落。釣りの撒き餌や養殖魚の餌として大漁漁獲されていたイサダが、全く売れなくなってしまうという状況に。なんとか人間の食品用に新鮮なまま凍結保存ができないかと、アライアンスパートナーである「三陸とれたて市場」では商品開発が進められていました。
当時、刺身用途に仕上げられたイサダをS N Sにアップしたところ、一人のアクアリストから「観賞魚の餌として分けてほしい」という連絡があったのだそう。その要望がきっかけとなり、イサダを観賞魚用餌料とする研究がスタート。約4年の研究開発期間を経て「Natural Ecosystem Module ®︎」が発売されました。

ヒト向け食品として販売するよりも、このような市場に対して提供を行えば三陸の海の価値より高単価で販売できるかもしれないと考えた土方さん。「視点を変えることで、これまで価値のなかったものの見方を変えることができる」と話します。
「Natural Ecosystem Module ®︎」を主に購入するのは、観賞魚に並々ならぬ愛情を持つ “ハイアマチュア”なアクアリスト。一般的な餌料では、希少価値の高い魚の健康を保つのが難しいと経験から分かっている人たちです。そんな彼らに、どんな点が評価されているのでしょうか?

製品の特徴の一つに、精密凍結技術・C A S(Cells Alive System)が用いられていることが挙げられます。iPS細胞の凍結にも使われるなど、再生医療の現場でも成果が認められている技術です。
この高度な凍結技術により、餌料を解凍する際に出るドリップを減らし、水槽が汚れるのを防ぐことができます。また、新鮮な状態のまま凍結させることができるため、自然本来の餌料を与えることができるといいます。

三陸エンリッチメント研究室の製品開発には、もう一つ大きな強みが。それは、地元の漁業者たちとの強固な信頼関係が築かれていること。漁獲時期の情報を提供してくれるだけでなく、「めずらしい魚が入ったから取っておいたよ」と、忙しい合間を縫って協力してくれる漁師さんもいるそう。
三陸の海の魚が良質なのは、温暖な海流と寒暖な海流がぶつかる漁場で漁れるため。「どんなに高度な凍結技術があっても、凍結加工時の魚の鮮度や状態をそれよりも前に、つまり時間を戻すことはできない」と土方さんが話すように、質の良い魚が漁れる環境にあり、かつ地元の漁業者と密に連携しているからこそできる餌料の研究といえます。

「今後は、餌料の市場拡大を考えている」と話す土方さん。これまでの主な顧客は個人のアクアリストでしたが、これからは水族館や大学の研究室など、プロフェッショナルな現場でも製品を使用してもらいたいと考えています。
「そのためにも、今はより具体的なエビデンスを取得していく段階。魚ってしゃべらないですよね。だからこそ魚の目線になって、餌料や水槽のより最適な環境を探っていかなければならない。アクアリストが大事に育てている魚の命に対する責任がありますから。」

新たに何かを足すのではなく、もともと三陸の海にある豊かな資源を使い、自然そのままの餌料を魚たちに届けるという研究室のミッション。ひいてはそれが、水槽の環境を海と同じ生態系に近づけることができるかもしれないという秘められた可能性につながっています。
2025年は、新たな比較実験のプロジェクトが予定されているのだそう。製品を使用しているアクアリストからのフィードバックや、北里大学との協力体制のもと、その関係人口を増やしながら今後も研究は続いていきます。
(取材時期:2025年6月)
三陸エンリッチメント研究室に興味を持った学生さんにメッセージ!
「愚直なまでに、そのままに」ーーまっすぐに、ありのままを表現する。これは私たちの研究室のスローガンです。製品づくりも生き方も同じ。大切な最初の気持ちを信じて進めば未来は拓ける。僕も皆さんと共に挑み続けます。
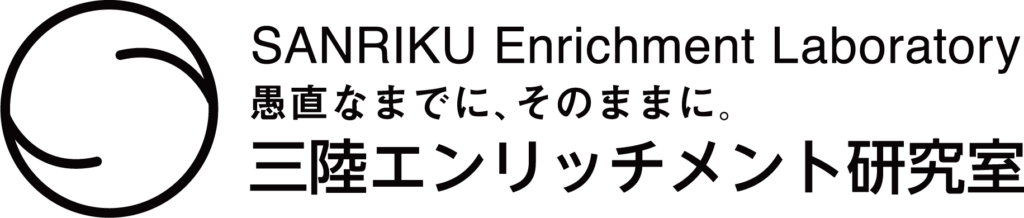
■三陸エンリッチメント研究室
2020年設立。いわて三陸の豊かな資源と高度な凍結技術を用いた精密凍結・活餌料「Natural Ecosystem Module®」の研究開発やオンライン販売、情報発信を行っています。「大船渡ビジネスプランコンテスト2021」、「第6回グッドアクアリウムデザイン賞2022 A Q U A Prize(特別賞)」を受賞するなどその取り組みは全国でも話題を集めています。